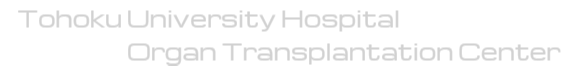![]()
東北大学は、わが国で最も早く1960年代から肺移植の研究をスタートし、今日に至るまで肺移植の基礎的研究を継続して来た唯一の施設です。臓器移植法施行後の2000年に日本で初の脳死肺移植に成功し、以来2024年12月までに206例の肺移植(脳死肺移植187例、生体肺移植19例)を実施しました(図1)。主な適応疾患は、リンパ脈管筋腫症、肺高血圧症、間質性肺炎などです(図2)。当施設は、現在、東北・北海道では唯一の肺移植実施施設となっています。
東北大学では、生体臓器移植にともなう生体ドナーのリスクと臓器機能低下をできるだけ回避するという倫理的な観点から脳死移植を優先する方針をとっており、実施例の約90%が脳死肺移植です。一方、やむを得ず脳死肺移植を待てない方や体格の小さな小児などを対象に、生体肺葉移植を19例実施しました。生体肺葉移植は一般に2人の提供者を必要としますが、体格の小さな小児では提供者が1人でも十分な肺機能が供給される場合もあります。生体肺葉移植19例のうち、このような1肺葉移植をこれまで2例実施しました。
東北大学肺移植における各術式のレシピエントの生存率を図3に示しました。東北大学における肺移植の全術式によるレシピエントの術後5年生存率は73.89%、10年生存率は66.03%であり、国際心肺移植学会の登録の成績を大きく上回る良好な成績が得られています(図4)。
![]()
呼吸器疾患によって肺の機能が低下し、あらゆる薬物治療によってもその進行が抑えられず、病気の進行に伴って酸素吸入などの補助にもかかわらず生命が危険におびやかされるような重症呼吸不全に陥った患者さんに対する唯一の根本的治療法として肺移植があります。肺移植手術とは、悪くなった肺を提供者(ドナー)から提供された肺と取り替える手術と言えます。脳死肺移植は、脳死となった方から片側または両側の肺を、生体肺移植では一般的に2人の提供者からそれぞれ片側の下葉を提供していただいて、それを患者さんの病気の肺を取り除いた後に移植します。
肺移植は心臓、腎臓や肝臓などの移植と同様に欧米では臓器不全患者さんに対する一般的な治療法として定着しています。今日では世界で年間4500件を越す肺移植手術が行われており、累計手術数は6000件を超えています。日本においても1997年10月に臓器の移植に関する法律が施行され、脳死下での臓器提供が法的に可能となりました。1998年4月に、東北大学、京都大学、大阪大学、岡山大学、2005年に獨協医大、福岡大学、長崎大学、2013年に千葉大学(再認定)、2014年に東京大学が脳死肺移植実施施設に指定されました。2019年末までに526例の脳死肺移植が施行されています。生体肺移植についても保険診療で認められているのは上記9施設であり、2019年末までに234件の生体肺移植手術が行われました。
![]()
肺移植治療の対象となるレシピエントは、下記の条件を満たす方です。
- 治療に反応しない慢性進行性肺疾患で、肺移植以外に患者の生命を救う有効な治療手段が他にない
- 移植医療を行わなければ、残存余命が限定されると臨床医学的に判断される
- レシピエントの年齢が、原則として、両肺移植の場合55才未満、片肺移植の場合には60歳未満である
- レシピエントが精神的に安定しており、移植医療の必要性を認識し、これに対して積極的態度を示すとともに、家族および患者を取り巻く環境に充分な協力体制が期待できる
- レシピエントが移植手術後の定期的検査と、それに基づく免疫抑制療法の必要性を理解でき、心理学的・身体的に充分耐えられる
![]()
肺移植が必要と考えられるレシピエントでも、肺移植による救命が難しい場合があります。
下記のような問題がある場合には、肺移植の適応から除外します。
- 肺外に活動性の感染巣が存在する
- 他の重要臓器に進行した不可逆的障害が存在する(悪性腫瘍、骨髄疾患、冠動脈疾患、高度胸郭変形症、筋・神経疾患、肝疾患(T-Bil>2.5mg/dL)、腎疾患(Cr>1.5mg/dL、Ccr<50mL/min))
- きわめて悪化した栄養状態
- 最近まで喫煙していた症例
- 極端な肥満
- リハビリテーションが行えない、またはその能力が期待できない症例
- 精神社会生活上に重要な障害の存在
- アルコールを含む薬物依存症の存在
- 本人および家族の理解と協力が得られない
- 有効な治療法のない各種出血性疾患及び凝固異常
- 胸膜に広範な癒着や瘢痕の存在
- HIV (human immunodeficiency virus)抗体陽性
![]()
- 1. 肺高血圧症(肺動脈性肺高血圧症、アイゼンメンジャー症候群など)
- 2. 特発性間質性肺炎(IIPs)
- 3. その他の間質性肺炎(膠原病や薬剤が原因のものなど)
- 4. 肺気腫
- 5. 造血幹細胞移植後肺障害(GVHD)
- 6. 肺移植合併症(気管支吻合部狭窄など)
- 7. 肺移植後移植片慢性機能不全(CLAD)
- 8. その他の呼吸器疾患
- 8.1 気管支拡張症
- 8.2 閉塞性細気管支炎
- 8.3 じん肺
- 8.4 ランゲルハンス細胞組織球症
- 8.5 びまん性汎細気管支炎
- 8.6 サルコイドーシス
- 8.7 リンパ脈管筋腫症
- 8.8 嚢胞性線維症
- 9. 上記に該当しないその他の疾患
![]()
肺移植登録から移植手術に至るまでおおよその待機期間は900日です。進行してから紹介を考える必要はなく、早い段階で足を運んでいただき、肺移植が将来、治療オプションになるかどうかの相談も受け付けております。
<移植施設へ紹介を考える目安(登録とは異なります)>
1.拘束性肺障害(特発性間質性肺炎や膠原病合併間質性肺炎など)
肺機能検査で%努力肺活量 <80%の場合、6分歩行検査でSpO2<90%を認める場合、
胸部CT検査で特発性肺線維症や上葉優位型肺線維症を認める場合
2.閉塞性肺疾患(慢性閉塞性肺疾患やリンパ脈管筋腫症など)
肺機能検査で%1秒量 <30%の場合、慢性呼吸不全を認める(在宅酸素療法を要する)場合
3.感染性肺障害(気管支拡張症やびまん性汎細気管支炎など)
肺機能検査で%1秒量 <30%の場合、慢性呼吸不全を認める(在宅酸素療法を要する)場合
4.肺循環性障害(肺動脈性肺高血圧症など)
プロスタグランジンI2製剤を10 ng/kg/minで治療されている場合
<日本臓器移植ネットワークの資料>
待機期間や移植登録の流れがまとめられています。
ニュースレター 2022年
https://www.jotnw.or.jp/files/page/datas/newsletter/doc/nl26.pdf
日本の移植事情
https://www.jotnw.or.jp/files/page/give/give02_sourcebook.pdf
![]()
肺移植適応決定のために必要な主な検査は以下のとおりです(病状により項目は変わります)。
- 胸部X線
- 胸部CT
- 気管支鏡検査・経気管支肺生検
- 血液ガス
- 肺機能検査
- 心電図
- 心エコー
- 肺血流スキャン・換気スキャン
- 心臓カテーテル検査(右心カテーテル検査、左心カテーテル検査)
- 6分間歩行テスト
- 免疫学的検査・ウイルス抗体価
- 喀痰培養
- 血液・尿一般検査
- 腎機能検査
- 便潜血
- 腹部エコー
- 胃内視鏡検査
- 他科的検査(精神科、歯科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、産婦人科など)
検査を東北大学病院で行うか、主治医(紹介医)のもとで行うかは患者さんの病状にもよりますので、移植コーディネーターに御確認下さい。登録の過程において、移植医と移植コーディネーターによるインフォームドコンセントが2回義務づけられております。
![]()
東北大学呼吸器外科では、肺移植に関連する以下の臨床研究を実施しております。
<肺移植患者におけるCOVID-19ワクチンの有効性と安全性関する前向き研究>
2019年に発生が確認された新型コロナウイルスは、瞬く間に世界的流行(パンデミック)に至り、人類の脅威となっています。新型コロナウイルス感染症は、世界中で死亡者数も積み上げているものの、効果が期待できる抗ウイルス薬は未だ開発されていません。そのため、2020年冬より実用化された新型コロナウイルスワクチンはパンデミックを抑制できる可能性がある手段として注目されています。海外からは臓器移植患者さんでも安全性や有効性を確認する報告が相次いております。そのため、本研究では、東北大学病院を受診される肺移植患者さんの新型コロナウイルスワクチンでどれほどの副作用が生じるのか、また、ワクチン接種前後でどれほど新型コロナウイルスに対する抗体を獲得できるのかを確認します。対照(コントロール)群(移植既往がなく免疫抑制剤を使用していない者)を置く非ランダム化前向きコホート研究です。
本研究は Yahoo!基金「新型コロナ医療崩壊防止活動支援助成」を受けています。
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCT1021210009
<肺移植登録後の予後また待機中死亡に関連する因子の検証>
肺移植は進行した呼吸器疾患に対して有効な治療法のひとつです。かかりつけ医が呼吸器疾患を有する患者さんを移植施設へ紹介するタイミングや移植施設で肺移植登録する目安は、日本では明確な指針がなく、全ての患者さんが肺移植の機会を得られていないことも考えられます。待機期間中に亡くなられる患者さんもいます。呼吸器疾患によってどのようなタイミングで移植登録が行われ、肺移植まで至っているのかどうか把握する必要があります。日本の全ての肺移植施設で、肺移植登録患者の登録時情報(年齢、性別、移植適応疾患、呼吸機能、運動耐用能、血液検査)とその予後(移植、待機継続、死亡)を調査します。また、登録疾患別の予後に関連する因子を検討する多施設前向き研究です。
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000046880